「なんとなく体が重い」「肌荒れが続いている」「便秘がち」――
もしかしたらその不調、自律神経の乱れが原因かもしれません。
でも、自律神経は自分でコントロールすることができない“自動調整システム”。
だからこそ、自分の状態を知り、腸を整えることが自律神経を整える近道になるのです。
今回は、自律神経と腸の関係に詳しい、順天堂大学医学部教授・小林弘幸先生監修のセルフチェックを通じて、あなたの「自律神経のバランス」を見える化。
今のあなたに必要な整え方のヒントが見つかるかもしれません。
まずはチェック!10の質問であなたの“バランス”を確認
下記の10項目の質問に、それぞれ当てはまる選択肢を1つだけ選んでください。
選んだ項目に応じて、★(副交感神経)と☆(交感神経)カウントします。
「-★☆」は、それぞれマイナス1点として計算してください。
※出典:小林弘幸著『名医が教える 自律神経できれいになるメソッド50』(ポプラ社)

【1】睡眠
- 夜、布団に入るとすぐ眠れる(★☆)
- 睡眠時間は十分なのに昼間眠くなる(★)
- 夜、なかなか寝つけない(☆)
- 眠りが浅く、夜中に起きる(-★☆)
【2】仕事・家事
- 「やらなければ」と義務感で行動する(★☆)
- なかなかやる気が出ない(★)
- やる気があり、やりがいもある(☆)
- 「やらなければ」と思うが、腰が重い(-★☆)
【3】食生活
- おいしく食事ができる(★☆)
- どちらかというと野菜中心(★)
- どちらかというと肉中心(☆)
- 食欲不振またはドカ食いが多い(-★☆)
【4】胃腸の状態
- 胃もたれや胸焼けがあまりない(★☆)
- 食べてもすぐお腹が減る(★)
- 胃もたれや胸焼けが多い(☆)
- 食事前後に胃が痛くなることが多い(-★☆)
【5】体重と体型
- 3年以上、体重に大きな変化はない(★☆)
- ついつい食べ過ぎて太り気味(★)
- ストレス太りしやすい(☆)
- ここ1~2年で5kg以上増減した(-★☆)
【6】手足の冷え
- 年間通じて冷えを感じることが少ない(★☆)
- 体が温かく、眠くなることもある(★)
- どちらかというと冷えやすい(☆)
- 冷え性で、肌の調子も悪い(-★☆)
【7】メンタルヘルス
- オンとオフの切り替えが得意(★☆)
- ストレスはないが、ボーっとすることが多い(★)
- 1日中、気が休まらない(☆)
- 考えるのが嫌で、寝て思考放棄する(-★☆)
【8】日々の疲れ
- 疲れても、一晩寝れば元気になる(★☆)
- 昼間、眠くなったり、だるくなる(★)
- 疲れるが、仕事だけは頑張れる(☆)
- 疲れが抜けず、何事もおっくう(-★☆)
【9】トラブル時の反応
- 解決策を考え、行動に移す(★☆)
- 考えても考えがまとまらない(★)
- 考えすぎて不安になる(☆)
- 考える気すら起きない(-★☆)
【10】人生の充実度
- やる気があり、心身ともに充実(★☆)
- マイペースでのんびり過ごしている(★)
- 刺激的な毎日で活動的(☆)
- 漠然とした不安感がある(-★☆)
計算方法
- ★の数を合計
- ☆の数を合計
- 「-★☆」はそれぞれ−1個で計算
診断結果:あなたの自律神経タイプは?
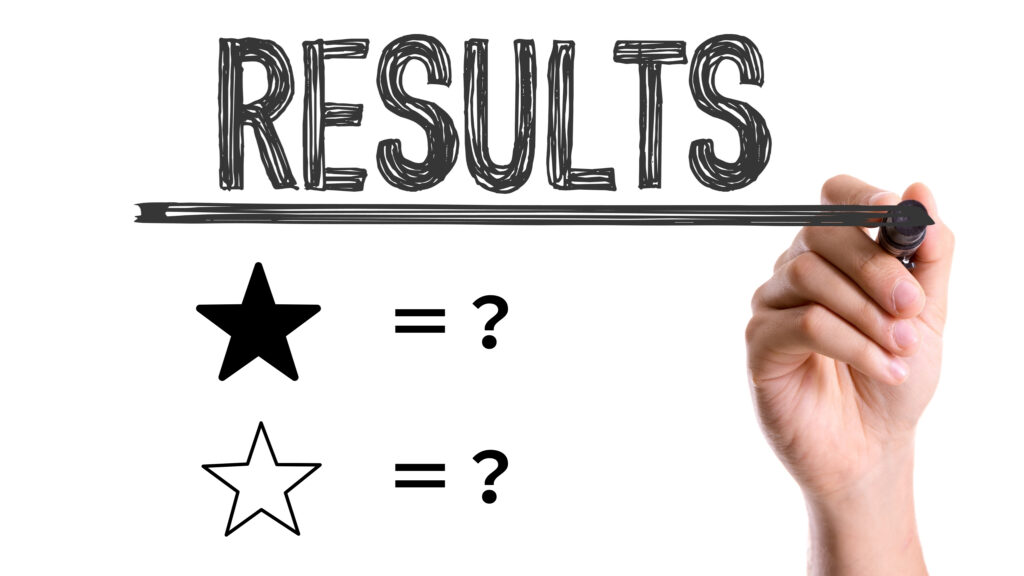
合計した★と☆の数から、以下の4タイプのどれに当てはまるかを確認しましょう。
■タイプ1:太りにくい「理想」タイプ
★と☆がともに8個以上
交感神経・副交感神経ともにバランスよく高く働いている理想型。
この状態が続くように、睡眠・食事・運動のバランスを維持しましょう。時々バランス診断の振り返りをするとなおOK。
■タイプ2:血流が悪い「ストレス」タイプ
★が7個以下、☆が8個以上
交感神経が高く、副交感神経が弱いため血流が滞りやすいタイプ。
太りやすく便秘がちに。ぬるめのお湯の入浴や笑顔、吸う:吐くが1:2の呼吸などで、リラックスを心がけて。
■タイプ3:ムラがある「マイペース」タイプ
★が8個以上、☆が7個以下
副交感神経が高く、交感神経が弱いためやる気は起きず疲れやすい傾向。
朝の光や朝食で生活リズムを整える意識を。また適度な運動、両手をバンザイにしてハッハッと短い息を吐く呼吸法も◎。
■タイプ4:疲れすぎている「ぐったり」タイプ
★・☆ともに7個以下
心身ともに疲労し、自律神経全体の機能が低下。
まずは規則正しい生活で心と体を休ませる時間を意識して。ウォーキングやストレッチもおすすめ。
タイプを知れば、腸活のヒントが見える
腸と自律神経は、相互に影響し合う関係にあります。
どちらが乱れても、体や肌に不調が表れやすくなるのがこの2つの関係。
- 自律神経が整えば、腸の動きがよくなる
- 腸内環境が整えば、自律神経も安定する
つまり、自分の自律神経の状態に合わせて腸に目を向けることが、腸活を成功させる第一歩なのです。
まとめ
「なんとなく不調」は、見えない自律神経のサインかもしれません。
でも、そのバランスは腸を整えることで改善できる可能性があります。また、副交感神経は年齢とともに活性が落ち、腸内環境も年齢とともに悪くなってくるもの。放っておけば、両方とも悪化し老化が進み、肌荒れもしやすくなり、健康面にも心身ともに様々な悪い影響がでてきてしまいます。
腸活というと、ビフィズス菌の摂取など、食生活だけ見直せばいいと考えている方は多いと思いますが、腸活は、食事、運動、睡眠が三種の神器。
まずは、自分のタイプを知ること。
そして、日々の生活の中で「食事・運動・睡眠」の三本柱を意識することで、腸内環境は少しずつ整っていきます。
次回は、小林先生おすすめの「1分腸活」をご紹介予定です。
タイプを知ったうえでの実践編、ぜひお楽しみに!
あわせて読みたい
今回教えてくれたのは…
-
順天堂大学医学部教授/日本スポーツ協会公認スポーツドクター : 小林弘幸
自律神経と腸の研究の第一人者。著書に『名医が教える自律神経できれいになるメソッド50』(ポプラ社)、『医師が教える1分腸活』(自由国民社)など多数。
記事をシェア